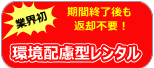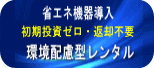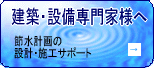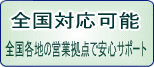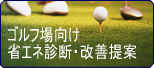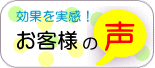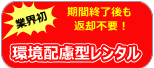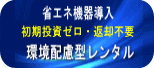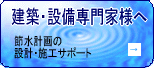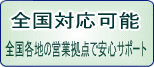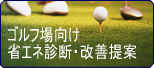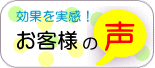|
(1)予報円の情報
予報円は上記の通り、「予想される台風の中心位置」を表しています。
※視覚的に、予想される台風の大きさ や 予想される台風の発達状況 と勘違いしてしまいそうですが、あくまで、中心位置の予想です。
ちなみに、この予報円の中に入る確率は70%だそうです。
逆に言うと30%、つまり10回に3回は予報円を外れていることも忘れてはいけません。
(2)台風の大きさ=台風の勢力 ではない
台風の指標の中には「大きさ」と「強さ」があります。
気象庁では、
台風の「大きさ」を「強風域(平均風速が15m/s以上の風が吹いているか、吹く可能性がある範囲)」、台風の「強さ」を「最大風速」でそれぞれ区分しています。
台風が大きいほど強風域の範囲は広くなるため、被害は広範囲に及びやすくなります。
ただ、台風が大きいほど、台風の勢力が強くなる、というわけでもありません。
(2019年台風15号の例)
台風15号は2019年9月9日に千葉県千葉市付近に上陸し、暴風による建物被害のほか、千葉県を中心に大規模な停電なども発生しました。
台風15号は上陸時の強風域の半径が200kmほどと比較的小さな台風でした。
一方で、勢力は比較的強く、本州への接近時は「非常に強い」勢力にまで発達しました。千葉市で最大瞬間風速57.5メートルを観測するなど、千葉県内各地で記録的な暴風となりました。
気象庁は顕著な災害をもたらしたこの台風15号について、災害の経験や教訓を後世に伝承することなどを目的として「令和元年暴走半島台風」と名称を定めています。
このように、コンパクトな台風でも甚大な被害をもたらすことがあります。
台風情報の確認時には、予想進路や暴風警戒域の範囲だけでなく、勢力などの風の強さについても確認するようにしましょう。
(3)台風接近時に確認したいその他の情報
実際に台風が接近しているときは台風と併せて他の情報を活用することが大切になります。
多くの人は「警報・注意報」や「雨雲レーダー」などを確認する習慣があるかと思いますが、是非確認していただきたいのが、「河川の増水や氾濫に関する情報」です。
特に大雨によって引き起こされる災害の危険度を示す情報である「キキクル(危険度分布)」も確認する習慣をつけたいですね。
「キキクル」は、大雨による災害発生の危険度の高まりを5段階で色分けして地図上で確認できる気象庁が公開している情報です。これまでは雨量が注目されることが多かったですが、雨量だけでは分かりにくかった各地域の「災害の危険度の高さ」が面的にわかり、自主的な避難の判断に活用できます。
|