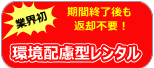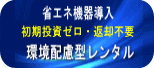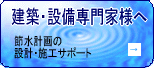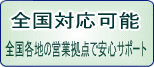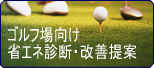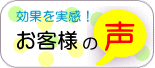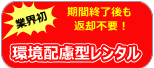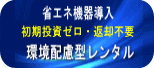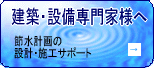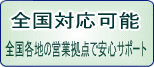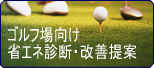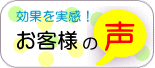■9月10日は下水道の日
「下水道の日」は、諸外国に比べて著しく遅れていたわが国の下水道を全国的に普及さ
せるためのPR活動のひとつとして昭和36年に「全国下水道促進デー」として始まりました。
当時、わが国の下水道普及率は、わずか6パーセントでした。
それから約40年が経過し、日本における近代下水道の基である旧下水道法が制定され
た1900年(明治33年)から100年を迎え、その記念行事が行われたこと、また、2001年(平成
13年)が21世紀のスタートの年にあたることなどから、近年の下水道に対する認識の高まり
もあり、この際、より親しみのある名称として「下水道の日」に変更されることになりました。
■なぜ、9月10日なのか。
下水道には、家庭などから出る汚水を浄化してから自然に返す、という役割のほかに、雨
水をすみやかに流し、街が水浸しにならないようにするという、大事な役割もあります。
1年を通して、短い時間に多くの雨が降るのは、8月から
10月の台風シーズン。中でも、立春(2月4日頃)から数えて
220日目にあたる日(9月10日頃)を二百二十日(にひゃくは
つか)と呼び、大きな台風が来る日とされていました。大雨
に備える特別な日のひとつだったのです。
この台風シーズン中の特別な日が下水道の雨水を流すと
いう役割となじみがあるとして9月10日を「下水道の日」と決
めたのです。 |
 |
■日本の下水道処理人口普及率
平成22年3月31日時点で、全国の下水道普及率は73.7%(下水道利用人口/総人口
)となっています。なお、都道府県別の下水道普及率は下の図の通りです。
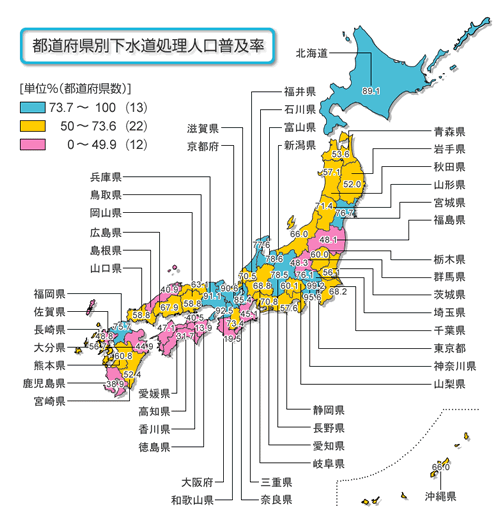
(出典:国土交通省)
■世界の下水道普及率
日本はこの50年間でわずか6%から73.7%まで下水道普及率があがったことがわか
ります。但し、実は日本の下水道普及率は先進国では低い水準にあります。
下水道の普及は先進国ほど進んでいる傾向があり、特に西ヨーロッパでは高い水準にあり
ます。その他先進国では、アメリカが71%と、日本とほぼ同じ水準にあります。
▼欧米諸国の下水道普及率
|
イギリス |
: 97% (1997年) |
|
ドイツ |
: 93% (1998年) |
|
フランス |
: 81% (1994年) |
|
アメリカ |
: 71% (1996年) |
ヨーロッパとの違いとして、日本では、河川が短く、海までの距離が短いので、問題が表面
化しにくかったため、このような実態になっていると考えられています。
一転、アジアの下水道普及率はどのようになっているのでしょうか。下の表はアジア5カ国
における下水道の普及率を表しています。一見、各国とも普及率は日本とほぼ同じ水準にあ
るように見えます。しかし、着目すべき点はやはり下水サービスを受けている人の数でしょう。
▼アジアにおける下水道普及率(2000年) (*人口は1000人単位)
|
| 国名 |
中国 |
インド |
インドネシア |
韓国 |
日本 |
| 都市人口 |
409,965 |
288,283 |
88,833 |
38,354 |
98,605 |
| 下水道普及率 |
68% |
73% |
87% |
75% |
70% |
| 非都市人口 |
857,953 |
725,379 |
125,275 |
8,940 |
27,490 |
| 下水道普及率 |
24% |
14% |
52% |
4% |
22% |
|
WHO・UNICEFはアジアの総人口ののうち、94%を調査し、そのうち約半数のわずか48
%の人々が、下水サービスを利用しているにすぎないと報告しています。
そのなかでも中国とインドは巨大な人口を抱えていることもあり、膨大な数の人々が下水
サービスを受けていないことが分かります。中国では都市で約1億3千万の人々が、非都市
地域では、約6億5千万人が基本的な下水設備を持たないことになります。
インドでは、都市で約7800人、非都市地域で約6億2千万人となります。
2000年にヨハネスブルクで開催されたミレニアム・サミットでは「下水サービスを享受できな
い人々の数を、2015年までに半減させる」という目標が立てられました。この目標を達成する
ためには、その大部分を中国、インドで実施する必要があることを示唆しています。
また、中国、インドを含めた開発途上国では下水設備が整備されていても、ただの排水溝
の役割しか果たしていない場合や処理施設が適切な機能を果たしていないケースが多々存
在しています。そのため各国の普及率の数値は必ずしも適正なサービスが行き届いているこ
とを意味しないこともあります。
9月10日「下水道の日」を記念して各地では各団体によるイベント開催も多く予定され
ています。
日本または世界においての下水道の現状をふまえ、改めてその役割、その重要性につ
いて考えてみる機会にしてみてはいかがでしょうか。
*参考文献−国土交通省(下水道資料室)
|